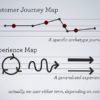HCD-Net フォーラム2015 要約メモ 〜IoTから組織デザイン、UXDのキャリアパスまで〜
こんにちは、@h0saです。
2015年5月30日に開催された、HCD-Netフォーラム2015(1日目)に参加しました。
HCD-Net主催のイベントやWSに参加し始めて2年目になりますが、HCD-Netの活動は今年で10年目になるそうです。
[参考] 昨年の参加メモ:HCD-Netフォーラム2014 参加メモ 〜デザイン思考/UXD/おもてなし〜 | UX INSPIRATION!
タイトルにもつけた通り IoT や組織デザイン、UXDのキャリアパスの話など、多様で興味深い話ばかりでした。
個人的にはLINE森川氏のお話とSITE4D隈元氏のお話はグッとくるものがありました。
以下、それぞれの講演の要約をメモします。
Contents
「HCD-Netのこれまでとこれから」黒須正明氏
初めはHCD-Net理事長の黒須氏のお話。HCDのこれまでの10年とこれからを話されました。同様の内容が以下の記事に載っているそうです。
[browser-shot url=”http://u-site.jp/lecture/hcd-net-10-years” width=”250″ height=”200″]
この10年で、ユーザビリティやHCD、UXが取り巻く環境が大きく変貌したのだと再確認しました。
「新しい企業のマネジメントスタイルとイノベーション」森川亮氏
森川氏は様々なメディアでも取り上げられた通り、2015年3月にLINEの代表取締役社長を退任され、自身のスタートアップC Channelを立ち上げられました。
お話を聴いて感じたのは、森川氏はいわゆるデザイン的な考え方を大事にしている、ということです。
あまりに共感できる内容だったので、その日のうちに著書をkindleで本を購入してその日のうちに読破してしまいました。
さて深い話は別の機会に譲るとして、特に印象に残ったお話をまとめます。
変化は予測できない
・変化を予測するのでなく、変化に常に対応することが大事
・昔は長期の事業計画を立てていたが、それを3ヶ月単位に変えた
・計画を作っても共有はしないまま、随時変えていったらうまくいった
→これはMIT伊藤穰一氏の「地図ではなくコンパスを持て」の話と共通しており印象に残りました。
野球型よりもサッカー型
・野球はポジション、フォーマットが決まっている
・サッカーはもっとフレキシブルで、キーパーがシュートする場合もある
・未来が予測できない今、その場で判断して自ら動いて提案していける人じゃないと生き残れない
→野球とサッカーの例えはなるほど、と思いました。特に人数の少ないベンチャーのような組織においては、迅速な判断と時として職域をまたいだ行動も大切だと日々感じています。
作る時間を長くする
・日本企業は「何を作るか」という仕様書を作る時間が長く、ものを作る時間が短い
・世界で競争するには高品質なものを早く出すべき。限られた期間の中でできるだけ作る時間を長くする必要がある
・今求められているものは必需品よりも付加価値。よりものをシンプルにしてスピードを重視するべき
→これはもうその通り、といった感じで非常に共感しました。アジャイルやリーン・スタートアップの考え方に通じますね。
C Channel について
・日本を元気にするには、若い人を元気にすること
・今は若い人が共感するメディアがない。若い人が共感するメディアを作りたい
・これまでの動画は横長で、これは劇場から来ている。スマートフォン時代は動画が縦長になる
・日本の財務体制を変えるには、新しい産業を作って世界へ展開したい
→純粋にカッコイイ、と思える講演でした。
「情報の視覚化のデザイン」隈元章次氏
隈元氏はSITE4Dという情報の視覚化を得意としたデザインスタジオの代表の方です。
様々な事例を動画とともにご説明いただきましたが、今僕が業務で携わっていることとかなりシンクロして、とてもテンションが上がりました。
隈元氏がこれまで仕事してきた内容をまとめると、「連動、感知、追尾、記録、予見」という5つの言葉に集約されるとのことでした。
いくつかの事例がYoutubeにアップされていたので貼り付けます。
他にも、サッカーのトラッキングシステムのビジュアリゼーションや、札幌ドームのディスプレイUI、エグゼクティブ用の経営コックピットなど、刺激的なプロジェクトが紹介されました。
今までは上記5つの言葉単体に収まるプロジェクトが多かったが、これからはこの5つが組み合わさるプロジェクトが多くなる、とのことでした。センサー技術やAIがどんどん進化している現在、まさにそう思います。
「融けるデザイン」渡邊恵太氏
続いて、明治大学総合数理学部先端メディアサイエンス学科専任講師であり、『融けるデザイン ハード×ソフト×ネット時代の新たな設計論』の著者である渡邊恵太氏のお話。同著は読了済でとても興味深い本だったので、お話を聴くのを楽しみにしておりました。
講演の内容としては『融けるデザイン』の概要版といったところでしたが、実際にデモンストレーションや映像を見せていただいたことで、より理解が深まりました。
以下、紹介されていた事例のいくつかを貼っておきます。
[browser-shot url=”http://www.persistent.org/VisualHapticsWeb.html” width=”250″ height=”200″]
[browser-shot url=”http://www.persistent.org/cursorcamouflage.html” width=”250″ height=”200″]
[browser-shot url=”http://high-awareness.org/products/integlass/integlass.html” width=”250″ height=”200″]
インタラクションデザインに興味があり同著が未読の方は、一読をオススメします。
「ISO国際標準:Human Centred Organisation」持丸正明氏
産総研サービス工学研究センター センター長の持丸氏からは、「ISO/DIS 27500:Human Centred Organisation」についての紹介がありました。
普段実業務に携わっていると、ISOといった標準化の話はなんとなく「めんどくさいなぁ」と個人的には敬遠しがちでした。
しかし、今回ご紹介いただいたのは、人間中心的な「組織」に関する標準化への取り組みについて。UXの議論をしていると、多くの場合「組織」の話に行き着くことが多く、ホットなトピックだと感じました。
また関連する話題として、”Enterprise UX (EUX)”があります。昨月5月に米国 San Sntonio で世界初のEUXカンファレンスが開催されたそうで、詳細は以下の記事に詳しいです。
参考:企業戦略として注目されるEnterprise UXとは? | NCデザイン&コンサルティング株式会社
Human Centred Organisation, Enterprise UX ともに「組織」にフォーカスしており、今後の動向が注目されます。その際、以下の視点を区別していきたいです。
- 組織全体「が」HCD/UXDに取り組むのか【組織が主語】
- 組織全体「へ」HCD/UXDを適用するのか【組織が目的語】
「サービスデザインのこれから」武山政直氏
サービスデザインと言えば、應義塾大学経済学部教授の武山先生。
今回のお話で印象に残ったのは、「サービスエンタングルメント(Service Entanglement)という概念です。
Entanglement とは、「もつれ/絡み合い」という意味。つまりサービスエンタングルメントとは「サービスとサービスの入り交じり」という意味です。
これはCMUのEunki Chung氏が提唱した概念とのことで、検索して出てきた以下のスライドが参考になりました。
IoT化の加速により、サービス同士の連携がより重要になるのは間違いないでしょう。サービスデザイナーには、サービス同士を俯瞰するよりマクロな視点が求められるのだと捉えました。
「UXDの職能要件とキャリアパスについて」竹部陽司氏
最後に、UXデザインの職能要件とキャリアパスについてのお話。リクルートテクノロジーズの竹部氏が登壇されました。
リクルートはクライアントとカスタマーをマッチングさせるという「リボンモデル」が有名ですが、その裾屋を広げるのがUXデザインとのことでした。

出典:リクルート
そのためには、サービス成長フェーズに合わせて最適なUXを提供する必要があり、それと共に流動的に職能要件も変化するとのことです。
例えば「新規期」ではUXデザイナーにプロダクトオーナーとしての職能も求められたり、「成長期」「成熟期」ではディレクターとしての職能も求められる。
むしろ職能要件から、職種を決める流れになっているそうです。
僕自身、大企業(成熟期)からベンチャー企業(新規期)に転職して、求められる職能が大きく変化したので、この話には大いに納得感がありました。
リクルートテクノロジーズは最近良い噂しか聞かないので、このようなキャリアパスの事例含め、動向に注目していきたいです。
パネルディスカッション
持丸氏、武山氏、竹部氏、そしてモデレーターのコンセント長谷川氏で行われたパネルディスカッションで、1つ印象に残った話があったのでメモしておきます。
「製造業のサービス化」について。
僕は前職は製造業に在籍していたので、この「製造業のサービス化」は課題感として持っていました。
持丸氏いわく、「製造業のサービス化」はコンソーシアムを作って取り組んでいるそうです。しかし、メーカーが抱える課題は以下とのこと。
- グッズドミナントロジックという過去の成功体験を持っており、なかなか抜けられない
- 大量に作って大量にばらまく体制が、個別のコンテクストへの対応が必要なサービスデザインの考え方に合わない
- 製品はやめても問題ないが、サービス(例えばヘルスケアサービス)はやめたら大変になる
- 変化が速いのがサービス、そこに対応できない
個人的にもやもやしていたものが言語化され、なるほど、と思いました。これらの課題を打破したメーカーが日本経済を救うと信じています。
おわりに
以上、HCD-Netフォーラム2015で行われた講演の要約メモでした。
インタラクションデザインの話からサービスデザイン、組織の在り方についての話まで、幅広くとても興味深い話が多く、改めてHuman Centered Design という分野の奥深さを感じさせる一日でした。
参考文献
人間中心設計のフォーラムということで。